第六話 牙城クスコ(6)
一方、クスコを逃れた山間部に張られたインカ軍の本営は、はじめての大いなる敗退に暗澹たる色を滲ませながら、夜闇の中に、灰色の影のようなその姿をボウッと浮き上がらせていた。
さらに、トゥパク・アマル及び側近たちの天幕の張られた界隈は、いつになく騒然とした雰囲気に包まれていた。
トゥパク・アマルが左肩から腕にかけて負った傷は、予想以上に重症だったのだ。
彼は意識こそ何とか保っていたものの、褐色の敵将、フィゲロアの刃によって深く切り込まれたその傷の痛みに、さすがに顔を歪めていた。
それでも、ひどく心配そうに見守る側近たちに、いつものように「大丈夫だ、案ずるな」と言って笑みを返そうとする。
しかし、その様子が今日はいっそう痛々しく周囲には映った。
すぐにビルカパサを治療したのと同じ、あの従軍医が呼ばれ、治療に当たった。
有能なこのベテランの医師も、その傷の深さにかなり深刻な目になっている。
常軌を逸する激烈な痛みがあるのに相違なく、にもかかわらず、トゥパク・アマルに意識が保たれていることに、従軍医は密かに驚愕したほどだった。
「様子はどうであろうか?」と、まるで自分が重症を負っているかのごとくに苦渋な表情を浮かべたディエゴが、喰い入るように医師に問う。
従軍医は恭しく礼を払いながら、深刻な口調で答えた。
「傷は相当深く、決して楽観できる状態ではありません。
すぐに手術をしなければなりません。
傷口を縫い合わせねば」
「手術…!!」
側近たちは、改めて固唾を呑んだ。
トゥパク・アマルも、微かに目を見開く。
従軍医は、寝台に横たわるトゥパク・アマルの顔の傍に、手術の合意を伺うように深く跪いた。
「トゥパク・アマル様…」
従軍医の真剣な眼差しに、トゥパク・アマルは頷き返す。
「世話をかける」
苦痛に耐えながらも、この従軍医の方に礼を払おうとするトゥパク・アマルの様子に、従軍医はいっそう深々と頭を垂れた。
それから、従軍医は急いでコカの葉を取り出し、トゥパク・アマルの方にそれを恭しく差し出した。
当地におけるコカは、「麻薬」というより、むしろ、鋭気を養い、苦痛を緩和する効用を有する珍重な薬用植物で、アンデスでは古来から愛用されてきた。
「トゥパク・アマル様、どうかそれをお噛みください」と促しながらも、従軍医は心の中でじっと思案する。
まともな麻酔などまだ無いこの時代、トゥパク・アマルに未だ意識があることは、手術を進める上では逆に不都合であったのだ。
このままでは、術中に伴う苦痛を、直接的に感じ取ることになってしまうであろう。
前記のコカや、また、他にもキニーネやセネガなどの麻酔効果のある薬草を利用するとしても、甚大な苦痛は避けられまい…――と、そろそろ初老の年齢にさしかかるこの従軍医の眉間の皺は、今、いっそう深くなる。
従軍医は暫し思案に暮れた挙句、ゆっくり顔を上げた。
いちかばちか、あの娘の不思議な力を借りてみよう…――!
「急ぎ必要な道具を取りに行って参ります」
そう言い残すと、従軍医は足早に本営の一隅に設けられた負傷兵の治療場に向かう。
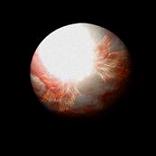
負傷兵でごった返したその場所は、思わず嘔気を誘うほどの血肉と汚物の臭気で満たされていた。
負傷兵たちの苦痛に呻く悲痛な声が、辺り中に渦を巻いている。
今回の戦闘における惨状を、そのまま象徴しているかのようなあまりにむごたらしい情景であった。
その雑踏の中に足を踏み入れながら、従軍医は近くで看護に当たっていたインカ族の女性に声をかける。
「コイユールは、どこにいるかね?」
「コイユールなら、あちらに」と、その女性が指差した方向を見やると、目を覆いたくなるような重症を負った兵の傍に、ガックリと肩を落として身を屈めるようにしているコイユールの姿があった。
従軍医がそちらに急いで歩み寄ると、銃弾に撃ち抜かれた傷口からとめどなく血を流した兵が、今まさに、その最後の息をひきとったところであった。
その兵の前で、治療のために彼女自身の両腕をもおびただしい真紅の血に染めたまま、深く首をうなだれている。
従軍医は、瞬間、声をかけることがはばかられたが、しかし、思い切ったように「コイユール」と、呼びかける。
従軍医の声に僅かに顔を上げたコイユールは、その目に涙を滲ませ、悲嘆と悔しさとに満ちた、ひどく苦渋な表情である。
従軍医はその目の色に応えるように、彼もまた苦しげに瞳で頷き、それから、コイユールに真っ直ぐ向き直って言う。
「すぐにトゥパク・アマル様のお怪我の手術をしなければならないのだ。
手伝ってほしい」
「ええっ…――!
トゥパク・アマル様が、手術?!」
「シッ…!
他の者に聞かれたら、へたに不安を煽ることになる」
従軍医の言葉にコイユールはハッと口を押さえながらも、負傷兵が亡くなったばかりの冷めやらぬ衝撃に、新たな衝撃をぶち当てられたがごとくの悲痛と驚愕の表情で、身を震わせるようにしてその場に凍りついた。
「トゥパク・アマル様が、そんなに大変なお怪我をされたのですか?!
そんな…手術だなんて…!」
周囲に聞こえないように声を押し殺して言いながら、ただでさえ苦渋に満ちたコイユールの表情は、みるみる蒼白になっていく。
従軍医は、深く眉間に皺を寄せた深刻な表情で「そうなのだ」と頷く。
「すぐに手術をしなければならない。
おまえに、手術中の痛みを和らげてほしいのだよ」
コイユールは、思わず目を見開いた。
「でも…!!
そんな…手術中の痛みをとるなんて、私、やったことがありません…!」
「コイユール、そんなことを言っている場合ではないのだ。
たいそう酷いお怪我を負われているのに、トゥパク・アマル様は意識がおありになるのだ。
手術に伴う激痛は、鎮痛の薬草だけでは間に合わぬ。
確かに、おまえの力がどれほど効果があるかはわからぬが、何もせぬよりは、可能性に賭けてみたい。
とにかくやってみておくれ」
従軍医は非常に真剣な表情で、コイユールの顔を見据えている。
コイユールは、固唾を呑んだ。
しかし、意を決したように頷く。
もはや迷っている時間も、選択の余地も無いのだ。
「わかりました…やってみます」
従軍医も深く頷き返した。

それから、二人は大急ぎで手術の準備を整え、トゥパク・アマルの天幕に向かった。
天幕に入ると、やはりトゥパク・アマルは意識を保ったまま、自分の前に側近たちを集めて何やら話をしている。
「オルティゴーサ殿、そなたは全ての兵たちに軍の現状を伝え、十分にその労をねぎらっていただきたい。
決して、必要以上に不安を覚える必要はないと。
クスコを奪還できなかったことが、全ての終わりではない、と。
…そして、ディエゴ、そなたは、あのインカ族の敵将について情報を集めてほしい。
どんな些細なことでも何か知る者がないか、義勇兵たちも含め、広く聞き込みを行っておくれ。
そして、アンドレス、そなたは、兵たちの受けた被害状況を調べてきておくれ。
それから…」
搾り出すような苦しげな声であったが、各側近たちに澱みなく指示を送っていく姿に従軍医は目を見張った。
全く、あれだけの傷を負っていて、意識があるだけでも信じがたいというのに。
(このおかたは、何という強靭な精神力をお持ちなのだろう…――)
従軍医は、改めて、驚きと、密かな感動を抱きつつ、手術の準備を整えていく。
多分、このおかたなら術中の苦痛にも耐え抜かれるであろう、と、内心、算段しながら。
トゥパク・アマルの指示を受け、早速、各側近たちが天幕から散っていく。
アンドレスも立ち去りかけて、しかし、その時、ふと、コイユールの姿が目に入る。
にわかに高まる胸の鼓動を覚えながらも、彼女に気付かれぬよう距離を保ちつつ、そっとその横顔をうかがった。
コイユールは唇をギュッと結び、いつになく真剣な眼差しで手術の準備を進めている。
その目つきは、目前の大仕事への決意と緊張からか、ひどく険しくさえなっていた。
アンドレスの存在すら、今は全く目に入っていないようだった。
アンドレスには、従軍医が何故ここにコイユールを連れてきたのか、だいたい察することができた。
彼は己の胸に溢れ出す感情を抑えながら、この緊迫した現実へと自らの意識を懸命につなぎ止め、そして、今、コイユールのためにできる精一杯の気持ちを送ってみる。
(コイユール、頑張れ!!)
優しい微笑みをその目元に浮かべ、アンドレスは心の中で強くコイユールに呼びかけた。
不意にあたたかいものを感じて、ハッと振り返るコイユールの瞳の中に、天幕を出て行くアンドレスの後ろ姿が一瞬映った。
(アンドレス…!!)
瞬間、コイユールの胸にも切ないものがよぎる。
しかし、今はすぐに目前の重要な仕事に意識を戻した。
「それでは、トゥパク・アマル様、まずは、痛み止めの薬草をお飲みください」
従軍医の指示に従い、トゥパク・アマルが薬草を口に含む。
護衛のために天幕に残ったビルカパサが、彼もまだ癒えぬサンガララ戦での傷口に痛々しい包帯を巻いていたのだが、施術のはじまることを確認すると素早く天幕を出て、その入り口の外側に立った。
「トゥパク・アマル様、これから手術をさせていただきますが、御腕を切り、縫うなどございます。
薬草も手術に伴う痛みをとる役に立つとは思いますが…、誠に恐れながら、それだけでは十分ではございません。
こちらに連れて参りました娘は、手を触れるだけで、薬も何も使わずに痛みを和らげるという不思議な力をもっております。
手術の手伝いをさせたいのですが、よろしゅうございますか?」
そう問いかけると、従軍医はトゥパク・アマルの方に恭しく頭を下げた。
コイユールも、それに合わせるように、深々と頭を下げる。
従軍医は畏(かしこ)まりながら、改めて問う。
「トゥパク・アマル様、施術中の痛みを和らげるために、こちらの娘にトゥパク・アマル様の御腕に触れさせてもよろしゅうございますか?」
従軍医の深刻な声に、トゥパク・アマルはゆっくりと首を傾け、コイユールの方に視線を向けた。
コイユールはあまりの緊張から、すっかり身を固めて顔を上げられない。
「そんなに緊張せずとも良い」
トゥパク・アマルの静かな声に、コイユールは伏し目がちなまま、僅かに顔を上げた。
緊張の高まりからなのか、すっかり頬を上気させながら揺れるような瞳で己を見つめる彼女の方に、「よろしく頼む」と真摯な眼差しで言うと、トゥパク・アマルはすぐに真っ直ぐ天井の方に向き直り、目を閉じた。
従軍医はいよいよ真剣な表情になって傷口を確かめてから、緊迫感の中にも医師らしい冷静さを保った眼差しで手術道具を手に取ると、コイユールに目で合図を送る。
コイユールは意を決した表情で医師の目に頷き返し、それから、トゥパク・アマルの寝台の脇に跪いたまま、その両手をそっとトゥパク・アマルの左腕の傷口の傍に添えた。

トゥパク・アマルの引き締った筋肉の感触が、コイユールの細い指先にはっきりと伝わってきて、彼女は一瞬はじかれたようにその指を浮かした。
コイユールは己の指先を呆然と見た。
まるで電流に打たれたように、その指先が、ひどく痺れているのを感じる。
コイユールの心臓が、早鐘のように、恐ろしく速く打ちはじめた。
自分の反応の大きさに、彼女自身が驚愕しながら、トゥパク・アマルにその様子が悟られてはいまいかと慌てて目をやる。
が、幸いにも、彼は手術の開始に向けて精神統一をするかのように、じっと固く瞼を閉じていた。
決して苦痛を表に出さぬよう己の感情と感覚を厳しく律する気迫も相まってか、はじめて直近で見るトゥパク・アマルのその横顔は、コイユールの瞳の中で、ブロンズの彫像のように完全な均整を保ち、研ぎ澄まされ、息を呑むほど美しかった。
(ああ…落ち着いて、落ち着いて…――!!)
必死で自分をなだめながら、コイユールは再び、トゥパク・アマルの腕にその指を添えた。
心臓の鼓動が張り裂けそうに鳴り響き、本来は温かくなければ施術にならぬ指先は、逆に冷え切り、震えている。
コイユールはトゥパク・アマルの腕からまた指を離すと、己の両手を擦り合わせて懸命に温めようとした。
その額には、じっとりと冷や汗が滲んでいく。
しかし、従軍医がトゥパク・アマルの腕を紐で固く縛って止血し、それから、傷口に術具の刃物を近づけていく様子を見た瞬間、彼女の心はまるで色が変わるように、サッと冷め、急速に平静に戻っていった。
(トゥパク・アマル様に、痛みを感じさせてはならない…!!)
コイユールの指が吸い寄せられるように、トゥパク・アマルの腕に添えられる。
彼女は瞳を閉じると、いつもの太陽と月のシンボルを脳裏に描き、それから、秘伝のマントラを心の中で3回唱えた。
じっと意識をトゥパク・アマルの傷口に集中させる。
すると、いつものように上空からサッと光が彼女の頭上に降りてきて、頭から首、腕を経由して、そのまま手の平から、光がトゥパク・アマルの中に流れ込んでいくのが感じられる。
コイユールは、自分の意識を、高く、高く、上げていった。
頭上に射し込んでくる光の源を追い求めるように、射し込む光を逆に辿りながら上へ上へと進んでいく。

光の筋は上空の雲を越え、地球の成層圏を越え、やがて宇宙空間に飛び出して、さらに宇宙の果てまでも続いているかのようだった。
ふと見下ろすと、蒼く瑠璃色に輝く宝石のような地球が見える。
その美しさに恍惚と見入る彼女の意識はさらに高く昇り、眼下の地球もたちまち遠く吸い込まれるように小さくなって、やがて宇宙空間に霞んで見えなくなる。
コイユールは、さらに光の源を追って、宇宙のずっと果ての方までへも己の意識を飛ばしていった。
やがて、宇宙の遥か果ての方に、眩い巨大な塊のような光の源が見えてくる。
美しく、気高く、黄金色に輝くその光は、まるでインカのシンボル、太陽神の化身のようにさえ見える。
コイユールはその太陽のような光源の前で、深く跪き、祈りを送った。
(トゥパク・アマル様をお救いください。
トゥパク・アマル様の痛みを和らげてください。
トゥパク・アマル様に、たくさんの光をお与えください!
十分な光を、トゥパク・アマル様のもとに送ってください!!)
眩い光は、決して熱くはなく、ただ煌々と崇高な輝きを放っている。
コイユールは、己の意識を光源の前に飛ばし続けたまま、その神々しい光の前でひたすら祈った。
一方、トゥパク・アマルの天幕では、従軍医が黙々と治療を進めていた。
トゥパク・アマルも、固く瞼を閉じたまま手術の進行に身を委ねている。
時折、「うっ…」と呻くことはあれども、一切、悲痛な声を上げることもなく、じっと従軍医の施術に耐えていた。
だが、その額に浮かぶ多量の発汗や閉じた瞼の震えから、表には出さずとも、実際には彼がどれほどの激しい痛みを感じているかは、この観察力の鋭い従軍医にはありありと推察できた。
それでも、幾分なりともコイユールの力が効を奏しているのか、トゥパク・アマル自身の精神統一による自己暗示によるものなのか、あるいは、その相乗効果のためなのか、ともかくも、トゥパク・アマルはその身を切られ、縫い合わされる所業に、意識を覚醒させたまま見事に耐え切っていたのだった。
従軍医は、その恐るべき強靭な精神力に深く感銘を覚えながら、一つのミスも犯さぬよう、慎重に施術を進めていった。
手術が開始されて、既に数時間が経過していた。
従軍医が、ふと横を見ると、コイユールは瞼を固く閉じ、トゥパク・アマルの腕に両手を添えたまま石のように微動だにせず、完全に意識がそこから離れた状態になっている。
ただ、その額からは、幾筋もの汗が流れ落ちていた。
トゥパク・アマルの傷口近くに添えられた彼女の指に従軍医がそっと触れてみると、まるで熱せられた鉄のごとくに、非常に熱くなっている。
彼は意識の無いコイユールの横顔に、静かに微笑みかけた。
(コイユール、頑張っておくれ!
もう、あと少しだ)
それから、従軍医は施術の仕上げに入っていった。
一方、意識を遥か宇宙の彼方まで飛ばしていたコイユールは、そのインカの神のごとくの黄金の光源の前で、今もひたすら祈り続けいている。
そろそろ手術の終わりが近いことを直観した彼女は、いっそう深くその光源に頭を垂れた。
(お力をくださり、お見守りくださり、本当にありがとうございました)
光に深く感謝の礼を払うと、コイユールはその光の前からゆっくり離れようとした。
その瞬間だった。
神々しいまでに黄金色の高貴な輝きを放っていたその光の源が、突如、赤黒く変色したかと思いきや、たちまち、溶岩が溶け出すように、ドロドロと液状に変容し、怒涛のごとく宇宙空間に流れ出したのだ。
コイユールがギョッとして立ち竦む目の前で、その赤黒い溶岩状の液体は、それまで白い星々が粛々と瞬いていた宇宙空間を、まるでその赤黒い溶岩の中に全てを呑みこんでしまうがごとくに、激烈な渦を巻きながら巨大化していくではないか――!!

「アアッ…これは…ああっ――!!!」
コイユールはひどい驚愕と共に、しかも、己の叫び声に耳を貫かれ、愕然としながらカッと目を見開いた。
そこは治療の行われていた天幕の中だった。
コイユールのその手はしっかりとトゥパク・アマルの腕に添えられてはいたが…――というよりも、トゥパク・アマルの腕を掴み、爪が食い込むほどにその指は硬直し、激しく力が入っていた。
彼女の額からは滝のように汗が流れ落ち、激しく肩を上下させるほどに息が上がっている。
暫し、己自身でも何か起こったのかわからず、コイユールは目をわななくように見開いたまま、焦点も定まらぬその瞳で呆然と宙を見据えた。
心臓が張り裂けぬばかりに、激しく鳴り響いている。
手術が終わり、丁度コイユールに声をかけようとしていた従軍医は、彼女のただならぬ様子に目を見張った。
そしてまた、トゥパク・アマルも、既にその目を開き、尋常ではない様子のコイユールを見た。
己に注がれる二人の視線に、コイユールは自分が本当に声を上げてしまったのだと悟った。
彼女は、いっそう蒼白になって、はじかれたようにトゥパク・アマルの腕から己の両手をはずした。
トゥパク・アマルの腕には、コイユールが思わず握り締めてしまった爪跡が残っている。
「ああ…申し訳ありません!!」
コイユールはさらに真っ青になって、その場に平伏した。
「コイユール、一体、どうしたのだ?」
従軍医の驚きと戸惑いの混ざった声に、コイユールは平伏したまま、後退(あとずさ)る。
そして、己が声まで上げてしまったことを激しく悔やんだ。
(い…今のは何?!…――予知夢?!
何にしても、あのような不吉なものを見てしまったなんて、このような大変な時に、トゥパク・アマル様に言えるはずがない…!!
なのに…それを悟られるようなこと…あってはならないのに…私は…!!)
コイユールは頭に血が上るのを覚えながら、僅かに頭を上げ、探るようにトゥパク・アマルの方に素早く視線を走らせた。
トゥパク・アマルの表情は相変わらず沈着そのものではあったが、何があったのだ、という目でこちらを見やっている。
コイユールの横顔を、冷や汗が流れた。
「な…何でもありません」と無理に平静を装って応えるコイユールの声は、しかし、明らかに震えている。
一方、トゥパク・アマルは、「声を上げていた。何か見たのだね?偽らずに申してみよ」と言いながら、鋭い目になって真っ直ぐにコイユールを見た。
トゥパク・アマルの、その貫くような視線に彼女は反射的に目をそらし、「いえ…何でもありません」と繰り返す。
(本当のことなど、決して言えない…!!
ああ…どうしたらいい…?!)
コイユールは頭が真っ白になりながらも、必死で言葉を探す。
トゥパク・アマルはコイユールの顔を見据えたまま、静かな、しかし、有無を言わさぬ、どこか強制力を秘めた口調で再び言う。
「そなたは、不思議な力を持っているようだ。
今、ここでそなたが見たものは、そなたを通じて、天がわたしに伝えようとしていることかもしれぬ。
偽らずに言ってごらん。
たとえどんなに良からぬことでも」
コイユールは、完全に引きつった表情で、トゥパク・アマルと床とを交互に見渡しながら、すっかり苦しそうな様子になっていた。
それでもトゥパク・アマルは、黙って、待っている。
ひどく重い沈黙の数分間が流れた。
見かねた従軍医が、諭すような口調でコイユールを促した。
「トゥパク・アマル様があのように仰っておられるのだ。
コイユール、申し上げなさい」
「でも…!」と苦渋に顔を歪めるコイユールに、従軍医は重ねて言う。
「コイユール、おまえの先程のような様子だけを見せておいて、何も話さないで終わってしまったら、周りはもっと不安になるものだよ」
「それは…」
コイユールがもう一度、トゥパク・アマルの方に視線を走らせると、トゥパク・アマルは「その者の言う通りだ」と低い声で言う。
ついに、彼女は意を決したように話しはじめた。
「恐れながら…先程見えたヴィジョンの中で…神々しく黄金色に輝く太陽のような光が、突然、赤黒い色に変わって…、その赤黒いものが溶岩のように宇宙に流れ出して、それから…、それから、その溶岩のようなものが…宇宙を呑みこんでしまいました…」
搾り出すような擦れた声で言うと、コイユールは、己の口から呪いの言葉を吐き出したかのようなおぞましい感覚に襲われ、思わずその手で口を押さえた。
トゥパク・アマルは黙ったまま、天幕の天井に目をやった。
その横顔を、不安定に揺れる蝋燭の光が音もなく照らし出している。
従軍医も息を呑んだまま、今更ながら、コイユールに話しを促してしまったことを悔やむように引きつった表情になっている。
コイユールは自分の手足が震えてくるのを感じ、そのまま、床の上に崩れるようにへたりこんだ。

そんなコイユールの様子に、トゥパク・アマルは再び彼女の方に視線を戻した。
そして、その切れ長の目元に、澄んだ柔らかな光を浮かべて、そっと微笑む。
「よく話してくれたね」
「トゥパク・アマル様!!
これは…これは、私の勝手な幻覚のようなものです。
私は、未来を予知する力など、少しも持ってはおりません。
ですから、どうか、どうか、決してお気に留めることのないよう…!」
コイユールの必死な様子に、トゥパク・アマルは頷き返した。
「わかった、そうすることにいたそう。
だから、そなたも、そなたが見たものを、この後、決して誰にも言ってはいけないよ」
コイユールは、涙の滲みかけたその目で、弱々しく頷いた。
これ以上コイユールに不吉なことを言わせてはまずい、とばかりに、従軍医が二人の間に割って入る。
そして、半ば諭し、半ば急(せ)かすように、コイユールを促した。
「では、そろそろ退かせて頂こう、さあ、コイユール」
しかし、コイユールは逆に、トゥパク・アマルの寝台の方へと近づいた。
そして、寝台のすぐ脇に膝をつくと、殆ど泣き出すのではないかと思えるほどのその顔を、しかし、今、きっ、と真っ直ぐに上げて、きっぱりとした声で言う。
「トゥパク・アマル様!!
あの…!
私、どうしても申し上げておきたいことが…!!」
既に天井に目をやっていたトゥパク・アマルが、少し驚いたように、再びコイユールの方に視線を戻す。
そこには、険しいほどに思いつめた、必死の眼差しのコイユールの姿があった。

「トゥパク・アマル様…私、子どもの頃、ビラコチャの神殿で、トゥパク・アマル様を、偶然、お見かけしたことがあるのです」
従軍医が、何を言い出すのかとばかり、驚いた表情になって慌ててコイユールを制しかける。
が、トゥパク・アマルはそんな従軍医に、構わない、と目で合図を送ると、「そうか。では、そなたも、わたしと同じティンタ郡の出身なのだね」と、変わらぬ静かな声で応えた。
「はい。
私は、トゥパク・アマル様が御領主様をされていたトゥンガスカの村で、農民の一人として生まれ育ちました。
トゥパク・アマル様…、私、あの神殿が大好きで…、幼い頃から、よく一人で訪れていたのです。
スペインに侵略されてからは、もう誰もいない神殿ですけれど、あそこに行くと、何か不思議に懐かしいような、心が呼び覚まされるような気持ちになれて…。
特に、夕陽に輝く神殿を見るのが、本当に好きでした」
「そうか。
確かに、夕暮れ時のあの神殿は、実に美しい」
トゥパク・アマルも、かの神殿の光景を思い描くように、どこか眩しそうな、懐かしそうな、遠くを見る目になった。
「はい。
それで、私、毎年、雪解けの季節になると、誰よりも早く、一番乗りで、あの神殿まで山を登っていたんです。
ずっと、幼い頃から…。
でも…、確か、あれは私が12歳になった年の春…、あの年はトゥパク・アマル様の方が私よりも早かった…。
いえ、もしかしたら、お会いできていなかっただけで、毎年、トゥパク・アマル様の方が、私よりも早く訪れていらしたのかもしれません」
何を言いたいのか、ともかくも、まるで何かに憑かれたような、必死な、懸命な瞳の色をして、しかし、どこか懐かしく思いを馳せるように夢中で話すコイユールに、トゥパク・アマルは無言のまま、ゆっくり頷いた。
従軍医がハラハラと見守る中、コイユールはトゥパク・アマルの寝台の脇にしっかりと膝をついたまま動こうとしない。
コイユールは息を継ぐと、身を乗り出すようにしながら、再び話しはじめた。
その必死の瞳に、今、清らかな光が宿りはじめる。
「私たちみたいに、植民地の時代に生まれた者たちは、生まれた時から、スペイン人に意味もわからぬままに蔑まれ、質素な生活どころか本当に惨めな暮らしの連続で、挙句は、強制労働で家族の命まで奪われる者も後を絶たず…、それでも、そういうものなのかって…皆…私も…どこかで諦めておりました。
でも、私、あの神殿で、偶然、はじめてトゥパク・アマル様をお見かけしたあの時、本当に…、本当に、インカの皇帝様が生き返ったのかと思ったんです。
本当に…嬉しかった…!!
トゥパク・アマル様は、とても光り輝いて見えて、力に溢れていて、神々しくて…ああ…インカの皇帝様って、こんなふうだったんだって思いました。
…それで、…それから、あのビラコチャの神殿でお見かけしてほどなく、アンドレス様のお屋敷で、トゥパク・アマル様をまたお見かけした時にも、トゥパク・アマル様が…そして、アンドレス様も…とても堂々として、力強くて、それでいて、人々を思う愛に溢れていると感じて…本当に輝いて見えて、ああ、本来のインカの人々は、こんなふうなんだって、そう思えたらすごく嬉しくて…。
インカの人々の…私たちの祖先の魂の輝きを、お二人の中にそのまま見る思いがして…本来の私たちを取り戻したいって、本気で思うようになりました。
そのためなら、私も、精一杯に頑張れると…、戦えると思えたのです!
きっと…そんなふうに思っているのは、私だけではないはずです。
義勇兵たちは、皆…いえ、きっと兵として参戦していない国中の者たちだって、私のように末端の農民たちまでも、皆…!
このクスコ戦でも、トゥパク・アマル様は敵の褐色兵を討たなかったけれど…あの中には、私たち農民たちの…極貧の者ほど、その親類縁者や知人たちが、少なからずいたはずです…。
今日の戦乱の最中(さなか)に、敵方の中にかつて知人であった者、親族であった者を実際に見出して愕然とした兵たちもいたと聞きます。
この本隊の義勇兵たちの中には、そのことを仲間同士で責める者もおりますから、末端の農民兵たちは皆…、貧しい隅々にいる者ほど沈黙しておりますけれど…その心の内では、たとえ今は敵方に回されようとも、どんな一人一人をもトゥパク・アマル様がお見捨てにならなかったことを、どれほど深く感謝し、心の中で手を合わせておりますことか…。
そんなトゥパク・アマル様が皇帝様として導いてくださるからこそ、私たちは進む道を信じて、誇りを持って戦える…トゥパク・アマル様は、私たちインカの人間たちの魂の源…、私たちの皇帝様…皆の希望の光なのです!!
だから…だから、絶対に、いなくなってはいけないのです。
ですから…さっきの、私の見たものは…あんなものは…!!」
コイユールは堰切ったようにそこまで言うと、むせぶように言葉に詰まった。
気付かぬ間に、幾筋もの涙が頬を伝って流れ落ちていた。
いつしか、従軍医も、コイユールを支えるようにその肩をそっと押さえながら、横に跪いている。
トゥパク・アマルは静かに目を細めた。
「そなた…アンドレスの屋敷と申したか?」と言ってから、遠い記憶を手繰り寄せるような表情になって、「もしかして、まだアンドレスが子どもだった頃…あの会合の時に何度か来ていた、アンドレスの友だったという、あの娘か?」と微かに目を見開いた。
コイユールは両手で涙をぬぐいながら、「はい…」と頷く。
「そうか…名は何と申したか」
「…――コイユールと申します」
「そうか、コイユール…。
そなたの思いは、よくわかった」
そう言って僅かに頷くと、言葉を継いだ。
「そなた、アンドレスとは、今も友なのか?」
コイユールは、一瞬、言葉に詰まる。
この数年間は、実際には、言葉の一つも交わせてはいなかったし、アンドレスが自分を今も友と思っているかも定かではなかった。
しかし、コイユールにとっては、それは「友」としてなのか…――あるいは、もっと違う存在としてなのか、いずれにしても、アンドレスは、今も言葉に尽くせぬ大切な存在であることに変わりはなかった。
コイユールは、「はい」と頷き、真摯な眼差しでトゥパク・アマルの瞳を見た。
「そうか…」と、トゥパク・アマルは、再び、ゆっくり頷き、目を細める。
「あのアンドレスは、危なげに見えるほどに純粋で、真っ直ぐなやつだが、潜在的には将たる器を持っている。
だが、あの者は、なにぶんまだ若く、未熟な点が多い。
しかし、いずれは、わたしではなく、あの者たちの時代になるであろう。
そのような時、真にアンドレスを支えてやれる者たちが必要だ。
コイユール、そなたのインカを思う気持ちをそのままに、この後も、アンドレスを支え続けてやってほしい」
「はい…トゥパク・アマル様…――」
コイユールは感極まって、もはや止まらぬ涙に目鼻も分からなくなったような顔を両手で覆ったまま、幾度も幾度も頷いている。
トゥパク・アマルも、揺れる蝋燭の炎を映したその瞳で優しく頷き返した。
そんなトゥパク・アマルとコイユールの様子を見計らうようにして、従軍医が二人の間にそっと入る。
「さあ、トゥパク・アマル様、これ以上、お話をされてはお体に障ります。
コイユールも、さあ、もう…」
トゥパク・アマルの体を気遣う従軍医の言葉に、コイユールは我に返ったように後ろに下がった。
最後にコイユールが寝台の上のトゥパク・アマルに視線を走らせた時、彼は既に真っ直ぐ上に向き直り、蝋燭の影の揺れる天井を黙って見つめていた。
従軍医とコイユールは深く頭を下げて礼を払うと、音を立てぬように天幕を抜ける。
そして、激しい疲労と興奮を引き摺りながらも、二人を待つ負傷兵たちの元へと深夜の道を引き返していった。
その晩遅く、トゥパク・アマルの天幕に他の側近たちが誰もいなくなるのを見計らうようにして、ディエゴが姿を現した。
トゥパク・アマルは寝台の上で、その左腕に大量の包帯を巻いたまま、じっと天幕の天井を見つめている。
麻酔の無い状態で、術後の激痛も常軌を逸するものがあろうに、相変わらず苦痛は表に出さず、まるで小さな波紋さえも浮かべぬ湖面のように恐ろしく静かな横顔だった。

トゥパク・アマルの寝台傍に灯された蝋燭は、その蝋の残りが少なくなり、揺れがかなり不安定になっている。
「トゥパク・アマル様、まだお休みではありませんでしたか」
ディエゴはゆっくりとトゥパク・アマルの方に近づくと、傍の琥珀色の木箱の中から新しい蝋燭を取り出し、それに火を灯して古いものと取り替えた。
彼の筋肉質の大柄な手の中で、蝋の少なくなった小さな蝋燭は、まるで消え入りそうに儚く見える。
一方、新たな蝋燭は、安定した光を煌々と天幕に放ちはじめた。
「お加減はいかがです?」と案ずる瞳で覗き込むディエゴに、トゥパク・アマルは静かに微笑み、「心配をかけてすまなかった。もう大丈夫だ」と応える。
「して、あの褐色兵の将のことは、何か分かっただろうか」と、問う。
ディエゴは微妙に頷いた。
「あまりはっきりしたことは分からなかったのですが、どうも首府リマの役人たちとつながった裕福な家の出身らしい。
名はフィゲロア。
もとは、真っ直ぐで、まじめな男だったようです」
「フィゲロア…」
トゥパク・アマルは思慮深い目になって、暫し、無言で新しい蝋燭の光を見つめた。
彼の切れ長の目元で、新たに燃えはじめた蝋燭の炎の放つ澄んだ光が、美しく反射して輝いている。
それから、彼は再びディエゴに視線を戻し、「ありがとう。よく調べてくれた」と心を込めて謝意を述べた。
ディエゴも、トゥパク・アマルの方に恭しく頭を下げる。
そして、再び顔を上げたディエゴの目の中に、まだじっと彼の顔を見つめているトゥパク・アマルの真っ直ぐな眼差しが映った。
「トゥパク・アマル様?」と、思わず、ディエゴが呟く。
「ディエゴ。もし、この後、わたしに何かあったら…」と言いかけて、トゥパク・アマルは、不意に己(おのれ)自身でも驚いたように、ハッと口を閉ざした。
思わずディエゴも目を見開く。
「トゥパク・アマル様、何を仰っているのです?!」
トゥパク・アマル自身も、予期せぬ弱気な言葉が己の口をついて出たことに、驚愕と苦渋の念を噛み締めた。
「すまぬ。怪我など負って、少々気弱になっているようだ」と、そして、「案ずるな」と前言を書き換えるように、はっきりとした口調で言った。
ディエゴは深く頷き、「このような時こそ、あなた様に強くあっていただかねばなりません。これからが正念場なのですから」と、太い武人らしい声で諭すように言う。
「そうだな」とトゥパク・アマルは頷き、目前の頼もしい従弟、ディエゴの勇壮な姿を改めて見つめ、目を細めた。
もし、わたしに何かあった時には、自分の後を受けて、この男がインカ軍の総指揮をとっていくことになるであろう…――と、そこまで考え、再び、はたと我に返って苦笑した。
まただ…、どうも今宵は本当に気弱になっている。
そんなトゥパク・アマルを、ディエゴも少々訝(いぶか)し気に見つめていた。
暫し長めの沈黙が流れ、それから、やや言いにくそうにディエゴが口を開く。
「このような時に、申し上げにくいことなのですが…、お耳に入れておいた方がいいかと思うことが…」
どこか所在無げな様子になり、口ごもりながら言うディエゴの方を、トゥパク・アマルが見た。
「何でも申してみよ」
その穏やかな声に、意を決したようにディエゴが話しはじめる。
「実は、フランシスコ殿のことなのです。
今日、戦場で、塹壕の中に蹲(うずく)まられて、ひどく震え、発汗も呼吸も激しくなっておられた。
何故、あのような状態でおられたのか全くわからないのですが…まるで敵の攻撃を恐れ、それから必死で逃れようとしているかのようにさえ見えました。
幸いお助けできたが、あのままでは、お命も危うかったものと存ずる」
そう言って、この猛将ディエゴにとっては全く信じがたいあの光景を思い起こすかのように、鋭く遠くを見据える目になった。
そのディエゴの目には、案ずる色と共に、苦渋と、そして、険しい色味が強く浮かぶ。
「そうであったか。
フランシスコ殿が…」
一方、トゥパク・アマルの声にも確かに苦渋の色が滲んでいたが、むしろ、深く案ずる色の方がずっと濃厚にうかがえた。
「フランシスコ殿はお心の優しい繊細なお方だ。このような血生臭い戦場は、あの方には耐え難いのであろう」と、静かな声で言うトゥパク・アマルの横顔を無言でうかがいながら、ディエゴは、それはあなた様のお気持ちでもありましょう、と心の奥で思う。
「しかしながら、この後も戦(いくさ)は続きます。このまま戦場に出られては、フランシスコ殿のお命が危ういのみならず、彼の指揮下にある軍勢の命をも危険に晒すことになりましょうぞ。何らかの対処をとらねばなりません」と、既に厳しくなった武人の声でディエゴが言う。
「うむ…」
トゥパク・アマルも、考え深げな目になり、再び、じっと天幕の天井を見やった。
ディエゴもつられるように、ふと天井を見上げる。
天井では、再び蝋の減りはじめた蝋燭の投げかける黒い影が、まるで二人に覆いかぶさる魔物のごとくに、ゆらゆらと不安定に揺れていた。

同じ頃、やはり、深い悲愴と苦悶の表情で、まるで溜まった空気の底のような不気味に静寂な深夜の闇の中で、草地に蹲(うずくま)るようにしているコイユールの姿があった。
トゥパク・アマルの治療の後、一旦、負傷兵の治療場に戻った彼女だったが、まるで仕事に手がつかぬ状態であった。
苦痛に喘ぐ負傷兵たちを前にしながら、しかし、己の手元のおぼつかなさから、かえって兵たちの症状を悪化させかねぬような強い危機感まで覚えるほどだった。
瀕死の兵たちを前にしながら、そのような己の状態にひどく嫌悪感を、そして、兵たちに対して深い罪悪感を抱きつつ、コイユールは逃れるように治療場を走りぬけ、己の寝所のあるビルカパサの天幕近くの草むらに走りこんだ。
とはいえ、他の兵たちも多くいる己の天幕に戻る気持ちには到底なれず、姿を隠すように、夜露を含んだ草の上にしゃがみこんだ。
そのまま息を詰めて、まるで銅像のように固まっていく。
その瞳には、いつしか涙が膨れ上がり、やがて頬を伝って流れた。
あれほど畏敬と憧憬の対象であったトゥパク・アマルと間近で言葉を交わせたというのに、その感慨を噛み締めるよりも、今は彼女の脳裏には、先刻のトゥパク・アマルの施術時に見てしまった呪わしい光景ばかりが嵐のように渦巻いていた。
神々しく黄金色に輝く太陽のような光が、突如、赤黒く変色し、その赤黒いものが溶岩のように宇宙に流れ出し、美しい宇宙を呑みこんでいく…――あのおぞましいヴィジョンを必死で掻き消そうとすればするほど、さらに濃厚に、強烈に、いっそうの臨場感を伴って喚起されてくるのだった。
否定しようとしても、己の見たものの信憑性をどこかで信じてしまう己自身も、非常におぞましく感じられた。
(あれは何を意味しているの?
…――破滅…滅亡…――死…――?!
まさか…ト…トゥパク・アマル様の…死?!…インカの滅亡…?!)
「そ…そんな…そんな…」
今、涙すらも氷ついたように止まっている。
コイユールは、自分の体温が急速に下がっていくのを感じた。
夏だというのに、激しい寒気がして、思わず己の両腕で自分の肩を抱き締める。
その細い指に、体の震える振動が伝わってくる。
これ以上、あの呪わしい光景の意味を決して考えぬように、コイユールは必死で思考を止めようとした。
しかし、止めようとすればするほど、思考は勝手に加速していく。
何かの言葉が頭をよぎろうとする度に、「あれは、ただの幻覚…幻覚…幻覚…!」と呪文のように声に出して言い続けた。
しかし、己の心までは、偽れない。
その心は、図らずも予見してしまったトゥパク・アマルとインカの暗黒の未来に対する、恐れ慄きと、絶望と、混乱とあまりに深い悲しみとで引き裂かれそうになっていた。
「どうしよう…アンドレス…、せめて、アンドレスに…」
朦朧としてきた意識の中で、無意識にその名を呟く。
その一方で、先刻のトゥパク・アマルの姿が、その言葉が、ぼんやりとした脳裏に甦る。
『そなたが見たものを、この後、決して誰にも言ってはいけないよ』
(トゥパク・アマル様…――)
いっそう混沌としていく頭の中で、しかし、最後にコイユールの脳裏をよぎっていったのは、やはりアンドレスの姿だった。
『アンドレス!!
…何とかして…――!!』
声にならない声で呟くように言うと、彼女の意識は事切れるように、そのままの姿で力尽き、混沌とした眠りの中に落ちていった。

そして、それからどれくらいたった頃だろうか。
明け方近く、ビルカパサの連隊に属する一人の黒人兵が、見張りの当番を終えて寝所へと戻る途中、たまたまその草地の傍を通りかかる。
そして、草の中に死んだようにうずくまって意識を失くしている女性の姿を発見した。
それが同じ連隊に属するコイユールだとわかると、その兵は急いでジェロニモのいる天幕に走った。
「おい、ジェロニモ、起きろ!!
おまえの知り合いのインカ族の女が、草の中に倒れてるぞ!」
「…――え?」
突然、その黒人兵に夢を破られ、寝ぼけ眼(まなこ)でジェロニモが起き上がる。
「なんだよぉ…一体…」
まだ寝ぼけたまま、その兵に急(せ)き立てられるようにして、ジェロニモが草地に向かう。
「ホラ、あれ!
おまえの知り合いだろ。
何とかしてやれよ」
目をこすりながらそちらをボンヤリと眺めたジェロニモは、しかし、草の中に死んだように倒れているコイユールの姿を認めると、顔色を変えた。
そして、走り寄る。
(コイユール…!!)
ジェロニモはコイユールの傍に跪くと、その呼吸を確かめる。
死んでいるのでも何でもなく、単に眠りに落ちているだけだとわかると、ホッと胸を撫で下ろした。
「何だよ…ったく、人騒がせだナ…」と、コイユールの方に呟くように言う。
しかし、完全に意識が飛んだ状態で、しかも、顔面蒼白にして、泥にまみれた悲痛な表情のままに倒れている姿は、やはり尋常を超えている。
「コイユール、起きろ!
こんなところで寝てると、カゼひくぞ!」
呼びかけながらコイユールの肩に手をかけ、その体をゆすってみる。
しかし、なかなか反応が無い。
「コイユール!!」
ジェロニモはさらにコイユールをゆすってみる。
すると、やっとコイユールは薄く目を開けて、朦朧とした瞳でボンヤリと宙を見た。
そして、消え入りそうな声で呟いた。
「…ア…――アンドレス…?」
「…!!」
(やっぱり…コイユール…アンドレス様のことを…――か?!)
ジェロニモが言葉を失っている先で、傍で見守っていた黒人兵が、「え?!アンドレスって、あの連隊将のアンドレス様のこと?!まさか…アンドレス様を呼び捨てにしたぞ!!なんなんだ、この女?!」と、憮然とした声を上げた。
「シッ!!
このことは、誰にも黙っとけ!」
きつい口調でその兵を制すると、ジェロニモはさらに力をこめてコイユールの体をゆすった。
「おい!!
起きろ!!
しっかりするんだ、コイユール!!」
そして、そのまま両腕を掴むと、コイユールの上半身を無理矢理起こした。
さすがに、コイユールもボンヤリとしながらも、その意識を取り戻す。
「え…?
ジェロニモ…?
あ…やだ、私…!」
次第に昨夜の記憶が戻ってくる。
(あのまま草の上で、眠ってしまったんだわ…!)
恥じ入るように咄嗟に両手で顔を覆うと、指の隙間から慌ててジェロニモに目で礼を送った。
それから、手を下ろすと、己に呆れ果てるように深く溜息をつく。
「ありがとう…私ったら…信じられない。
こんなところで…」
無理に引きつった笑顔をつくろうとしているコイユールから視線をそらし、ジェロニモは、ただ黙ってコイユールが立ち上がろうとするのを助けた。
「ちゃんと寝所に戻って、しっかり眠るんだ。さあ…」と、天幕の方に促すジェロニモの腕を制して、「いえ…。もう眠ったから、大丈夫。それより、治療場へ戻らないと…」と、コイユールは反対向きに足を進める。
「駄目だ!!
少しは、ちゃんと休め!!」
ジェロニモの剣幕に、コイユールは驚いて足を止める。
当のジェロニモ自身も、自分が声を荒げたことに決まり悪そうに、下を向く。
しかし、再び顔を上げると、諭すように言った。
「この戦(いくさ)、まだ先は長いんだ。
今、皆で共倒れになってる場合か?
いいから、今夜は、ちゃんと休め。
な、コイユール…」
いつもとどこかジェロニモの様子が違うと感じながらも、コイユールは観念したように頷いた。

寝所のある天幕の方へと戻っていくコイユールの後姿を、ジェロニモが見守る。
(コイユール…そうなのか?
アンドレス様を?
だ…だけど、なんで農民のコイユールが、よりによって、あの皇族中の皇族のアンドレス様なんだよ…?
無茶だ…こんなのって、ありかよ…?!
は…で、俺は…?
は…はは…ッたく、お話にもならねぇ…)
一方、隣で、黒人兵が、相変わらず憤然とした声を上げている。
「さっきの…うわ言?
『アンドレス』…って、あれ、何だ?!」
黒人兵が訝しげに首をかしげるのを、ジェロニモは再び険しい目で見た。
「いいから、それは忘れろ!!
俺には、そんなの聞こえなかったぞ。
おまえの、何かの聞き間違いだ!」
ジェロニモはまるで自分にも言い含めるようにそう言うと、「なんなんだヨ…おまえまでぇ…」と不満げにブツクサ言っている黒人兵の肩を押しながら、それぞれの寝所へと戻っていった。


